
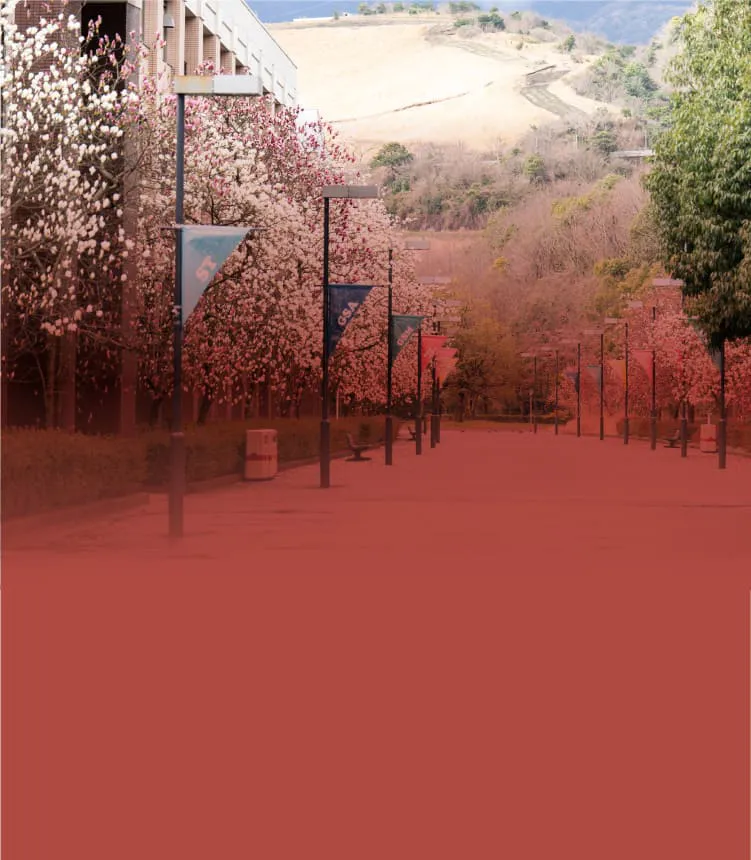
STEP 未来へと続く問いからの挑戦
留学もサークル活動も地域連携も起業も、自分の問いに挑戦し続ける未来や夢はAPUの学生の数だけあります。
頑張ることがカッコいい!そんな人たちが、いつもたくさんの刺激と勇気を与えてくれます。
事例3
支援の目が向けられにくい
小規模事業者の事業承継の仕組みをつくりたい
-

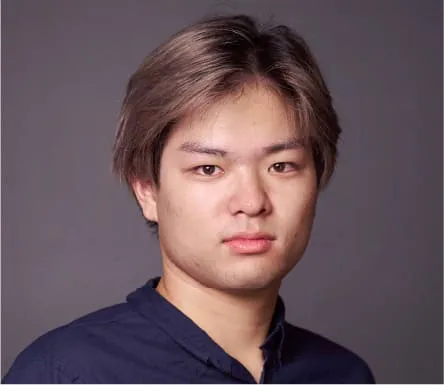
国際経営学部 3回生
桐谷 晃世 さん
事業承継プランナー
プロフィール:高校時代、課題解決に取り組むビジネスコンテストに出場し事業承継問題を知り関心を持つ。進学後、別府のシャッター街を目の当たりにし、地方の小規模事業者の事業承継が自分のやりたいことと気づく。2023年には経済産業省の社会起業家育成プログラムに最年少で選ばれ、そこでの学び・失敗を経て社会起業家への道を決意、邁進中。
深刻化する事業承継問題に直面し、地方で消えゆく小さな企業やお店を守りたい!
挫折の連続だった「社会起業家育成プログラム」に参加して得た気づきとは。
事業承継問題に取り組むことになったきっかけは?
幼い頃から、経営者である父の姿を見てきたことです。リーマンショックやコロナなど世の中の動きに左右される経営は大変だと、子どもながらにずっと感じていました。高校生のときにある地域の課題解決に取り組むビジネスコンテストに出場し、その過程で日本各地で深刻化している事業承継問題を知り、非常に関心を持ちました。その後、事業承継プランナーの資格を取り、M&A(企業の合併買収)や事業承継に関する会社でインターンを経験しました。
事業承継の志を抱き、APUに進学した理由を教えてください。
事業承継に関する知見が深まるにつれ、自分がやりたいのはM&Aや支援の対象から外れてしまう、街の小さなお店や町工場のような小規模事業者の事業承継だと気づきました。まさに別府もその課題に直面し、APUは地域性、国際性、多様性と共に多角的な視点を養える環境で、課題解決への学びができると考えたからです。実際にさまざまなバックグラウンドを持った人と交流してディスカッションを重ねていくと、たくさんの答えを与えてもらえます。
2023年に参加した経済産業省の社会起業家育成プログラム(通称:ゼロイチ)ではどのような学びがありましたか?
ゼロイチは社会課題を解決に導く事業活動に取り組む社会起業家の育成を目的としています。応募総数227名から最終10組、最年少で選んでいただき、シリコンバレーでの研修も含め7ヵ月間、本当に鍛えられました。それまでの「何とかなる精神」が通用しないことを痛感し、挫折だらけの日々でした。それでも常に自分に問いかけ、寝る間を惜しんで頑張る仲間と走り抜き、失敗は糧になることを学び、精神面でもビジネスのスキル面でも成長できました。

小規模事業者の事業承継について、今感じていることは?
日本の承継問題は、長い歴史のある酒蔵でも伝統工芸でも、地域の駄菓子屋さんでも、経営者の高齢化と後継ぎがいないことが要因となり、例え黒字でも毎年多くの企業が閉業せざるを得ない状況にあります。なかなかニュースにはならないですが、これは身近で大きな社会課題です。自分自身も行きつけだったラーメン店が、やはり後継ぎ問題で閉店したとき、一刻も早く成功モデルを作っていかなければ、との思いを強めました。
今後はどのような活動をしていきますか?
小さな会社やお店が承継される仕組みがないのなら、自分で作るしかない!という思いで、社会起業家への道を決意しました。まずは別府の商店街とタッグを組み、学生ならではのSNSの発信力を活用したり、お店の魅力づくりをしたりして、承継が可能な状態にします。それをAPUの卒業生や移住者、介護Uターンしてきた人などに受け継いでもらいます。もちろん資金とスキルも必要なので、企業や投資家、外部アドバイザーにも理解と協力を仰ぎます。
APUで得たその他の経験や学びがあれば教えてください。
「世界中を別府のファンに」をミッションに、別府の地域活性化活動を担う学生団体「旅べっぷ」の代表を2023年6月に受け継ぎました。街の魅力発信やイベント企画、地元企業のマーケティング支援などを行っていますが、もっと地域に根づいた多様な活動をするべく進化したいです。街と連携して実現する地方創生、地域貢献は、事業承継ビジネスにも深く関わる貴重な学びです。別府を拠点に成功モデルを生み出し、広げていけたらと思っています。








