
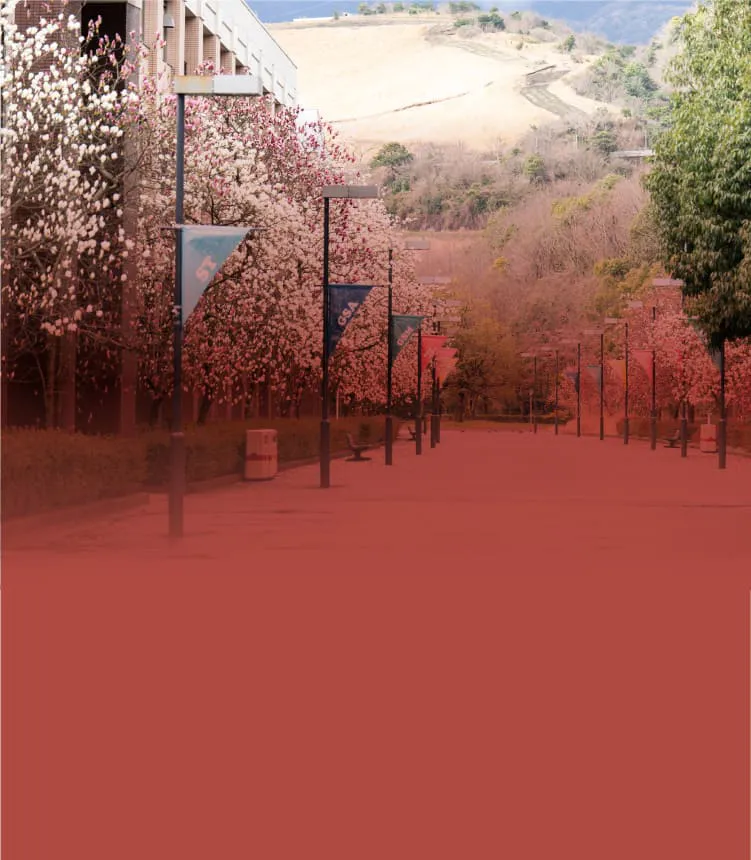
STEP 未来へと続く問いからの挑戦
留学もサークル活動も地域連携も起業も、自分の問いに挑戦し続ける未来や夢はAPUの学生の数だけあります。
頑張ることがカッコいい!そんな人たちが、いつもたくさんの刺激と勇気を与えてくれます。
事例1 高校生と一緒に社会問題を考えたい
-


アジア太平洋学部 3回生
鈴木 悠栞 さん
学生団体「DUCT」代表
プロフィール:高校時代の探究学習に感銘を受け、探究的な学びができるAPUに入学。入学後、自身が高校生の探究学習を推進する側になりたいと決意し、APU公認学生団体DUCTに加わる。現在はDUCTの代表として、別府市内の高校生を相手に探究学習の授業を行う。
代表を受け継ぎ、よりよいサークル運営のために気づいて学んだこと。
何にでも挑戦できるAPUという環境の中で、将来の夢を形にしていきます。
現在、代表をしているAPU公認学生団体「DUCT」について教えてください。
世界中の社会問題を、DUCTのメンバーが先生役となり、おもに別府市内の高校生と一緒に考えていく活動をしています。例えば、環境問題を知るために、近くの餅ヶ浜の砂を借りて混ざり込んだプラスチックを探してみます。メンバーから出たアイデアなのですが、社会課題をただ見聞きするだけでなく、身近なものとして実感することでより深い気づきにつながります。他にも、夢の自由さについて語ったり、自己分析をしたり、さまざまな授業を行っています。
DUCTの代表になったきっかけは何ですか?
高校時代から社会問題に取り組む活動をしたいと思っていて、APUはその幅を広げるのに最も適した環境でした。DUCTには入学時に出あい、自分の考えや理念にぴったりと合っていたので嬉しかったです。先輩方が卒業するときに私1人になってしまい、絶対に続けていきたい!と決意して代表となりました。その後、まわりに声をかけていったら志を同じくするメンバーが増え、公認団体認定も受けました。現在は20名ほどが在籍しています。
代表として心がけていることは?
人数が多くなってくると、どうしても理由なく欠席する人が出てきます。それはなぜなんだろう? 参加したいと思ってもらうにはどうしたらいいのか? と考えるようになりました。運営や指示の仕方、会議のあり方、どんな活動をしていきたいか、大学の授業とスケジュールの管理方法などをメンバーとじっくり協議して実行した結果、出席が増えてきたので、柔軟な変化や工夫の大切さを改めて感じているところです。

DUCT以外の取り組みや今後の挑戦は?
地域課題の解決や社会価値を創造していく起業家を目指す人を応援する「ONE BEPPU DREAM AWARD」2023年のファイナリストに選ばれました。別府市を探究教育で活気のある街にしたい、地元の高校生たちの人間力アップにつなげたいというテーマです。準備も大変でしたし、厳しい意見もいただきましたが、悔しさをバネにして頑張り、視野も広がりました。2025年には、「次世代共創リーダー育成プロジェクト」の一環として、DUCTのメンバーと大阪万博にブース出展する予定です。
大学で好きな授業、印象に残っている授業はありますか?
清家久美教授の考え方にとても感銘を受けました。日常にも浸透して常に考えさせられる社会学で、「理解とは何か?何をもって分かるというのか?」という哲学にも結びつき、なぜこんな社会になっているのか、といった問題・課題に自ら近づくことができます。APUでの学びはまだまだ知らないこと、面白いことがたくさんあって、疑問に思ったり、悩んだり、考えたり、気づいたりを繰り返しながら、多角的に広がっていくのが楽しいです。
将来の夢を教えてください。
APUや学生と連携して、一緒に何かを考え、高校生も大人もみんなで探究力を持って成長していける場(塾)を作りたいです。起業が目標ですが、今は知識や経験を積む時期で、社会に必要とされる力を蓄えていきます。APUには国内学生、国際学生、いろいろなバックグラウンドの人がいて、何にでも挑戦できる土台があり、周囲からの刺激や影響がモチベーションのベースになります。そして何よりも大切にしていきたいのが人と人とのつながりです。









