

DEEPEN
「問い」を深める
多彩なアプローチ
大学での主体的な学び方から、多様性・多文化のなかでの気づきと成長、
海外調査で広がる視野、研究の楽しさを知るゼミまで、
多彩なアプローチで問いを深め、ステップアップします。
INTERVIEW.01 価値観を問う。多文化協働ワークショップ
多文化協働ワークショップ
(MCW)とは?
多様な国・地域の学生が学ぶ環境を活かし、
異文化や価値観への理解、
国内・国際学生の交流を深めることを目標に、
日本人学生と留学生が同じクラスで学びます。
集大成は日英二言語で行う
プレゼンテーション大会です。
-

サステイナビリティ観光学部 1回生
鶴田 真帆 さん
-
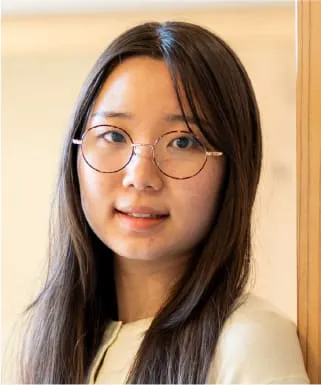
アジア太平洋学部 1回生
城田 果穂 さん
-

国際経営学部 1回生
園田 瑠衣 さん
1回生の必修科目である多文化協働ワークショップ(以下、MCW)ですが、
最初はどのような印象を持ちましたか?
園田さん:
私は寮に入っていて国際学生もいるので簡単な会話はするのですが、一緒に授業を受けて本格的に交流するのは初めてでした。それまで受けていた授業は日本語だけだったので、英語を交えて、どんな風になるんだろうという不安はありました。
鶴田さん:
国内学生3人と国際学生3人で1つのグループを作るのですが、最初から国際学生は容赦なく英語でどんどん意見を言うんですよね。他の2人の国内学生も英語が堪能だったので、ついていくだけで必死でした。
城田さん:
MCWは国際学生とディスカッションやグループワークをして、最後は自分たちで考えた「サマースクール」を英語で披露するプレゼン大会があります。初めにそのシラバス(授業計画)を見たとき、ワクワクと緊張が入り混じりましたね。
国際学生と接するうちに得た気づきや広がった視点、
自身の成長を感じることはありましたか?
城田さん:
サマースクールの案を出すときに、日本人学生は自然にフォーカスすることが多かったのに対し、私のグループの国際学生にはAIや技術、機械などに重きを置いた発想がありました。私自身にもない発想だったので、その人が持つ考えや文化や考えによって多角的な視点が生まれることを実感しました。
鶴田さん:
国際学生はマイペースな人が多いとも聞きますが、私のグループの国際学生はとにかくスピード感がありました。積極的に発言するだけでなく、作業や計画の進め方が早くて端的だったので、すごいなと思うと同時に自分にも良い影響になりました。あとは、国際学生が英語で書いた課題を日本語に訳すとき、難しい表現が出てきてもくじけずに、この解釈で合ってる?と本人に質問攻めしていました。解決できないのが一番つらいので、よりよい課題にしたいという一心でしたが、お互いの理解も深まり、自信にもつながりました。
園田さん:
最初は言語の壁が大きくて、本当に伝えたいことを上手く伝えられず、もどかしい思いをしたこともあります。でも、そこで諦めるのではなく、相手が言いたいことを引き出すような質問や相づちを意識すると、より自分の言葉で説明してくれるようになりました。聞き方や返し方しだいなんだと、大事なコミュニケーションの仕方を学びました。アクティブリスニング(積極的視聴)はMCWの目的のひとつなので、3人ともそこはとても磨かれたのではないかと思います。
鶴田さん:
新たな気づきといえば、グループの中での役割って自然に決まっていくんですよね。私は先の予定を決めて早めに考えながら進める性格なので、スケジュール調整やメンバーへの声かけをしていました。6人のバックグラウンドや事情が異なるのは当然で、ときには集まりにくかったり、モチベーションが変わってきたりすることもあります。でも、グループの課題は誰かに偏ることなく全員で公平に取り組むものなので、それをまとめて進んでいく必要があると思いました。
城田さん:
私も計画性があるタイプで、タイムマネジメントを担当しました。半年間の中で、どうしてもモチベーションや価値観の違いは出てきますが、そこで強い態度ではなく、やんわり伝える工夫をしてチームワークができていったのがうれしかったです。ディスカッションも初めの頃は自信がなかったのですが、意見には正解も不正解もないと気づいてからは躊躇しなくなりましたね。
園田さん:
私のグループは最初すごく高かったみんなのモチベーションが途中で一度下がってしまい、引き上げるのに苦労しました。でもお互いに補ったり励まし合ったりしながら乗り越えることができ、メンバーとはとても仲良くなりました。授業の最初のときの自分とは変わって、強くなったし柔軟になったし、英語も怖くなくなりました!

たくさんの苦労と学びの中で、グループで最終的に作り上げた
「サマースクール」はどんな内容ですか?また、プレゼンを終えた感想は?
鶴田さん:
大分県佐伯市をメインにキャンプや料理を体験する5日間のプログラムを考えました。ただ体験するだけでなく、その後の生活にも生かせるコミュニケーション能力や異文化理解能力を学ぶことを目的としています。対象は大学生から30代くらいまでの大人で、APUの学生にとっては“当たり前”な外国人との交流や活動環境に親しんでもらうのが特徴です。TA(授業をサポートする学生スタッフ)から、制限時間に正確に、個々の発表のバランスに気をつける、スライドをもっと分かりやすく、といったアドバイスをいただき、それも達成できて、プレゼン大会で1位になり感激しました!
園田さん:
私たちのプランは大学生向けに考えた、アラスカでのサマースクールです。目的はインターネット依存をやめ、オーロラや野生動物に触れながら大自然を感じてもらうことです。キャンプやクッキング、そして魅力ある特徴としてハンティングを取り入れました。できる限り現実的に安全に、例えば罠を設置して捕らえ、無駄にしないいただき方など命の大切さや循環をどう学ぶかという内容を大事にしました。みんなで走り抜いてやり切ったので、プレゼン後の達成感はすごかったです。
城田さん:
大分県のある山で1週間キャンプをしながらゴミ拾いをして、それを使って自分たちらしいアートを作る内容です。当初の予定だった本物のツリーハウスは難しいことが分かり、国際学生からミニチュアの案が出て決まったのですが、それで特徴を持たせることができました。みんなで進めていく中で、意見を言い合えている、ディスカッションをできていると感じられたのが何よりの喜びです。プレゼンでは最優秀賞をいただけて、たくさんのことを考えて、やってきてよかったと思いました。
APUに入学してよかったと思うことは何ですか?
園田さん:
いっぱいあるのですが、世界各国から日本各地からいろんな文化をもった学生がいて、多文化に日常的に触れられることが一番の良さです。その国や地域に行かなくても知ることができるって、すごいと思うんです。迷ったときにもいろいろな方面から気づきをもらえるので、自分の視野が広がって今後の人生をレベルアップできていくのではないかと感じています。
城田さん:
MCWでも実感したのですが、国内学生も国際学生も相手の意見を尊重して共感しあう雰囲気です。もちろん違う意見は出ますが、おのずとまとまって調和していきます。本当に多様な人がいて、起業していたり、留学していたり、沖縄出身で戦争のことをよく知っている人がいたり、貴重な知識や経験を日常生活のなかでシェアしてもらえます。APUに入学して、高校時代は小さなコミュニティの中にいて自信がなかった自分を大きく変えることができたと思います。
鶴田さん:
国際学生だけでなく、北海道から沖縄までさまざまな出身地の学生がいて、自分がやりたいこと、やってみたいことを誰も否定せずに、まわりが温かく見守って応援してくれます。私たち3人は、大学と協力して新入生を支援する学生団体「FLAG」のメンバーになりました。入学時の期待や不安をサポートする歓迎オリエンテーションの企画運営をします。書類と面接での選考があったのですが、MCWで培った経験と自信を糧に、希望をかなえることができたのは親身になって協力してくれた友達や先輩のおかげです。






